――インバウンド時代に考える「感謝」のかたち
2025年9月1日の朝日新聞で「日本の飲食店にチップはなじまない? インバウンド増加で店側も困惑」という記事を読みました。観光地の飲食店などでは、外国人旅行者がチップを渡そうとして従業員が戸惑う場面が増えているそうです。レジ横にチップボックスを置いたり、アプリで“投げ銭”機能を導入したりと、受け皿を用意する動きも出てきています。
でも、そもそも日本ってチップどうしてきたんだっけ?

日本の「チップ不要文化」
日本では昔から「サービス料は料金に含まれている」という考え方が強く、欧米のように10〜20%を上乗せする習慣はありません。旅館では“心付け”という形で仲居さんにお礼を渡す風習がありましたが、あくまで例外的。基本的には「チップは不要です」と胸を張れるのが日本のサービス業の特徴でした。
だからこそ、外国人旅行者から「これはチップです」と差し出された時、受け取っていいのか、断るべきなのか、現場が困惑するのもわかります。
いま、現場で起きていること
記事によれば、
- レジ横にボックスを設置して雑収入に
- アプリで任意チップを導入
- 施設の規約上、箱は置けない
など対応はバラバラです。
しかし、この仕組みだと結局「企業の収入」として処理されてしまうことが多い。渡した人は目の前のスタッフに「ありがとう」と伝えたいのに、会社に吸い上げられてしまうのは本来の趣旨とズレている気がします。
私はこう思う
チップ文化を日本に根付かせる必要はないと思います。ただ、せっかく渡そうとする人がいるなら、それは「感謝の気持ち」です。その気持ちは、ボックスやアプリを介さず、目の前の従業員に直接届く形が自然だと感じます。
もちろん「お断りする」のもひとつの選択肢です。でも「どうしても渡したい」という気持ちに対しては、従業員が個人として受け取れるようにしても良いのではないでしょうか。日本で高額のチップが常態化することは考えにくいのですから。
むしろ、そんな少額のお礼がその人のモチベーションを上げ、笑顔につながるなら、それはサービスの質をさらに高める好循環にもなり得ます。
結局は「ルールの徹底」次第
従業員が一番困っているのは「受け取っていいのか、断るべきなのか」がはっきりしていないからです。迷うからこそ戸惑いが生まれます。
- 基本は「チップは不要です」と伝える
- どうしても渡されたら個人で受け取ってよい
- 辞退する場合のフレーズを多言語で準備する
こうしたシンプルなルールを企業が決めて徹底するだけで、現場の混乱はぐっと減ると思います。
おわりに
日本の「チップ不要文化」は、世界に誇れる仕組みのひとつだと思っています。けれど、人の気持ちは国境を超えるものです。観光客が慣れ親しんだ習慣で差し出した紙幣には「ありがとう」の気持ちが込められている。それが企業の収入に吸い上げられてしまうのではなく、受け取った従業員に直接伝わるほうが自然で健全ではないでしょうか。少額であっても「自分の働きが評価された」と実感できれば、その喜びがサービスの質をさらに高める循環につながるように思います。私はそう考えます。





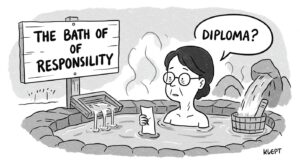




コメント