「また“国際基準”が来た」
日本の家族制度に、「国際基準」という言葉が降ってきた。
2026年4月から、離婚後も父母の双方が親権を持てる「共同親権」が導入される。
長らく日本では、離婚後に親権を持てるのは一方だけという「単独親権」が続いてきた。
「子どもの最善の利益を守るために」――法務省の説明はまっとうに聞こえる。
国連の子どもの権利条約、そして欧米の潮流に合わせるかたちで、日本もついに動いた。
だが、ふと立ち止まって考えてみたい。
この改革は、本当に“子どものため”なのか。
それとも“世界に遅れないため”なのか。
「世界標準」は万能薬ではない
共同親権は、欧米諸国ではすでに一般的な制度だ。
離婚後も父母が協力して子を育てる――それは家族の多様化と男女平等を象徴する「新しい家族のかたち」として評価されてきた。
しかし、同じ名前の制度でも、その実態には大きな違いがある。
たとえば北欧諸国では、共同親権を支える社会インフラが充実している。
カウンセリング制度、家庭裁判所の調停員ネットワーク、行政による養育費徴収システムなどだ。
親同士の対立が激化すれば、公的な調整チームが介入し、子どもの心理ケアまで含めて支援する。
それは「共同親権」というより、社会全体で子を育てる「共同養育」の仕組みといえる。
一方、日本の現場はどうか。
家庭裁判所の人員不足、心理専門職の少なさ、DV事案の線引きの曖昧さ――課題は山積している。
「共同親権」という法の言葉だけが整っても、それを支える現場の仕組みが追いついていない。
日本は「国際基準」というラベルだけを先に輸入し、その中身をまだ自前で構築できていないのだ。
“子の最善の利益”という便利な言葉
今回の法改正の根拠には、「子の最善の利益」という原則が掲げられている。
だがこの言葉ほど、耳ざわりがよく、同時にあいまいなものもない。
誰にとっての「最善」なのか――子ども自身なのか、親なのか、社会なのか。
その答えは、家庭の数だけ存在する。
たとえば、DVや虐待の被害を受けた母子家庭で「共同親権」が適用されたらどうなるだろう。
「父親にも関与の権利がある」という建前が、被害者への再接触を強いる危険性を孕んでいる。
制度はきれいに見えても、現実の家庭では「安全」と「共同」は必ずしも両立しない。
にもかかわらず、法の理念だけが独り歩きしている。
「子の最善の利益」という言葉が、結局は“誰のための利益”として運用されるのか――。
その監視こそが、いま最も必要とされている。
「共同」は本当に“平等”なのか
もうひとつ、見過ごされがちな誤解がある。
共同親権が「親の平等」を実現する制度だという見方だ。
確かに、これまでの単独親権制度では、母親が親権を得るケースが圧倒的に多く、父親が子どもと引き離される事例も少なくなかった。
「面会すらできない」「学校行事に参加できない」――そうした不公平を是正する狙いがあることは理解できる。
しかし、親の権利を拡大することと、子どもの幸せを守ることは、必ずしも一致しない。
「平等」という響きのよい言葉の裏で、親同士の調整負担や家庭裁判所での紛争が増えるリスクも潜んでいる。
子どもにとっては「二人の親の板挟みになる」という新たなストレスが生まれる可能性もある。
制度がどれほど公平に設計されても、感情の不均衡まで法は整えられない。
つまり、共同親権は「親の平等」ではあっても、「子の平穏」を保証するものではないのだ。
「正しさ」を急ぐ社会の危うさ
近年の日本社会には、「正しさ」を急ぐ傾向が目立つ。
ジェンダー平等、同性婚、選択的夫婦別姓、そして共同親権――。
どれも重要なテーマだ。
しかし「国際的に遅れている」という理由だけで進められるとき、そこには一種の焦りが滲む。
“正しいことを選ばなければ、取り残される”。
そんな空気が、政策を推し進める原動力になっている。
だが、「正しさ」を輸入するだけでは、社会の成熟は得られない。
制度を支えるのは法文ではなく、人々の理解と実践だ。
共同親権も同じである。
形式的な「共同」を整えるより、まずは家庭の現場で対話と信頼をどう築くかが問われる。
社会が「離婚=失敗」ではなく、「新しいかたちの家族」として受け止められる空気をつくること。
それこそが、制度改正よりも先に必要なのではないだろうか。
家族観という“文化”を見つめ直す
欧米の共同親権は、個人主義や権利意識という文化的基盤の上に成り立っている。
個人の責任と社会の支援がセットで機能する仕組みだ。
一方、日本の家族は、個よりも“つながり”や関係性を重視してきた。
だからこそ、離婚後も「世間体」や「親族の意向」に縛られやすい。
その中で「共同」を求められることが、どれほどの心理的負担を伴うか。
私たちは、「海外でうまくいっている」ことをそのまま当てはめる前に、自分たちの家族文化の土台を見つめ直す必要がある。
法律を変えることは比較的容易だ。
しかし文化を変えることには、時間がかかる。
そして、その時間こそが、本当の成熟を育むのではないだろうか。
「制度」よりも「支える仕組み」を
共同親権が機能するかどうかは、法律の文面だけでは決まらない。
親同士の対話を支援する体制、紛争を未然に防ぐ教育、経済的サポート、専門家による継続的な伴走――。
こうした“見えないインフラ”こそが、制度を支える土台となる。
どれほど整った法律も、それを実践する人と仕組みがなければ形骸化する。
「共同親権」という言葉だけが独り歩きし、かえって“親同士の対立を長引かせる装置”になることだけは避けなければならない。
結局のところ、この制度が問うているのは、“共に子を育てる社会”をどう築くかという、より大きな問いだ。
それは親だけの責任ではなく、学校、地域、行政、そして社会を構成する私たち一人ひとりの関わり方そのものである。
「国際基準」に追いつく前に、問うべきこと
いま私たちは、国際的な正解を追いかけるあまり、「自分たちの基準」をつくる力を弱めてはいないだろうか。
制度を変えることは、たしかに前進だ。
だが、それが「形だけの追従」で終わるなら、子どもたちの未来は何も変わらない。
共同親権の本質は、「親の関与」ではなく、「子どもを中心にした社会の再設計」にある。
そのためには、法を超えて、社会全体での“共同”が求められる。
国際基準に追いつくことよりも、
日本が「子どもの最善の利益」を自分たちの言葉で語れるようになること。
それこそが、本当の意味での“成熟した社会”への第一歩ではないだろうか。
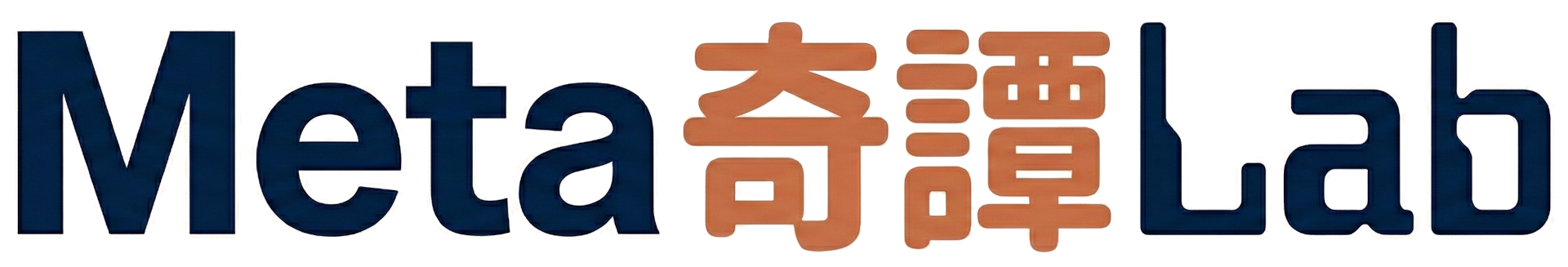








コメント